「 House of DNA 」 森太三・入谷葉子 (平面 / 立体 / インスタレーション他)
2012年6月20日 (水) ~ 7月8日 (日) [ 会期中 6月25日, 7月2日 月曜閉廊 ]
「House of DNA」 に寄せて
まず先にテーマありき、ではなく作家ありき、でこの二人展は企画された。 普段は1階と2階をメイン展示空間、3階をミニギャラリーとして使用し相互の作家の関係性を緩やかに潜ませながら展覧会を開催することが多いが、今回は森太三と入谷葉子というneutronではすっかりお馴染みの二人に同時期開催を打診した際、私は既にそれぞれの作品を直接的に関係させる趣向を思い描いていた。 だからこの二人展を仕組んだのは私であり、彼らはそれに応じてくれた図式となる。 neutron tokyoの白い建物がかつては人の暮らす家だったことを思い、彫刻作家・森 太三によるインスタレーションから生まれる抽象的なイメージと、平面作家・入谷 葉子の色鉛筆による「家」「家族」を題材としたドローイング作品を関係させ合いながら、人の住む家に流れる気配や存在する(した)歴史、あるいは鑑賞者であり展覧会の体験者でもある観客それぞれが、自分の家や家族を想起しながら、緩やかに場と作品に関係していくこと。 それによって、人と家との関係性が今までよりちょっと深く・素敵なものに感じられれば良いなと考えた次第である。
「House of DNA」という主題を提案してくれたのは入谷である。 二人の作家の色彩感覚の共通性と表現手法の差異こそがコラボレーションを成功させると確信していた私だったが、何かキーワードとなる言葉を探していた際に、既に二人それぞれがお互いの作品表現を思い浮かべていたのだろう、ふと入谷が口にしたのが「遺伝子」という単語であった。 森太三のインスタレーションによく見られる粘土粒を連結したものをDNAと見立て、入谷自身の制作が時間軸を超えて家族が繋がる(共有する)「家」をモチーフにしていることと関係させた上でのアイデアであり、秀逸だと感じたので採用したのだ。
森太三の表現は実に多様である。 彼は彫刻作家であると自称するが、一般的にイメージされるような彫像は一つとして生み出していない。 ほとんどは発表空間の特性を生かした上で会期中のみ作品として成立するインスタレーションの手法を取る。 つまり期間限定でその場限りの作品を生み出すのであるが、そもそも彫刻という概念は「彫る」「刻む」という行為によって生み出される立体作品ということよりも、或る空間に何かを置くことによって、それまでの空間が変化する(置いた物質によって空間が変貌する)ことを表現する意味で使われている。 だからこそ彼の表現は例え粘土の細かな一粒だったとしても、あるいは石膏の欠片であったとしても、それがそこに存在することに意味を持たせ、鑑賞者の想像力を誘発する装置となる。 淡い色彩の連続、あるいは微妙な形状の変化によるパターンは、素材が何であれ観る者を惹き付けてやまない。 最近では木の板の木目を生かしたドローイングでも、平面の上に彼ならではの抽象的で有機的な創造性を発揮している。
他方、入谷葉子は先述の通り「家族」が時間を超えて共有する「家」をテーマとして、ほぼ全て色鉛筆を用いて大小様々な図案を描くことで知られる。 もともと版画専攻でシルクスクリーンを用いながら色鉛筆を併用していたのだが、やがて後者に絞って制作が進んでいく。 今でもたまにシルクスクリーンやコラージュが見られるのはその名残であるが、画面にちょっとした違和感を生じさせるのは作家独特の空間構成の妙でもある。 実存する写真記録と、時に曖昧な自身の記憶を基にしながら、描かれるのは自らの生まれ育った家にまつわる事象である。 そこかしこのディテールに対する執着心と記憶力は作家の着眼点のユニークさを物語るが、実は私たち自身にも共感すべき要素がたくさん散りばめられている。 そう、入谷の表現は究極のパーソナルな出来事を基にしていながらも、人が住む「家」というテーマは実に普遍的で、象徴的なものでもあるのだ。 私たち人間は生きている限り常に何処かに居住し、その空間に依存するのだから。
こうして二人の異なる性質と空間に対する普遍的な意識が共鳴し、また新たな空間表現を生み出そうとしている。 インテリアとアートの関係性など遥か超え、ここに現出するのは「家」という概念と人間との遺伝子レベルの拮抗の姿である。
gallery neutron 代表 石橋圭吾 |
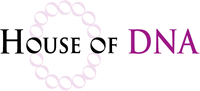 |